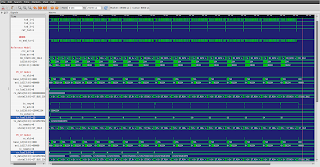この土日はあまり時間がとれなかったので、Standard FormatとExtend FormatのArbitration、Standard Format同士のArbitration、DLC(Data Length Code)を見た。
(Extend Fromat同士のArbitrationは既に検証済み)
Arbitrationに関しては何れも問題なく動作したが、波形的には従来見ているものと大差ないので、
今回はDLCについて書く。
CAN では1 Frame当たり0~8 Byte迄のDataを転送できるが、その転送長はCONTROL FIELD内
の4bitのDLC(Data Length Code)で表す。

転送長とDLC各bitとの対応は上記のとおりである(Dを0、Rを1と見れば普通のBinary表現)が、
転送長が0~8の9種であるのに対してDLCは2^15 = 16通りある。
CAN では8以上は8と解釈することになっている。(CAN Specification 2.0 Addendum page 1)
上図はDLCを0~15迄振ってNode1から送信をした場合であるが、DLCが8以上では転送長は8に丸められている。
上図はRemote frameでDLCを0~15にした場合だ。
Remote frameはData転送を要求するFrameなのでRemote Frame自体にはData転送は無い。
従って、DLC0~15の各Frameの長さは同一になっているのが判る。